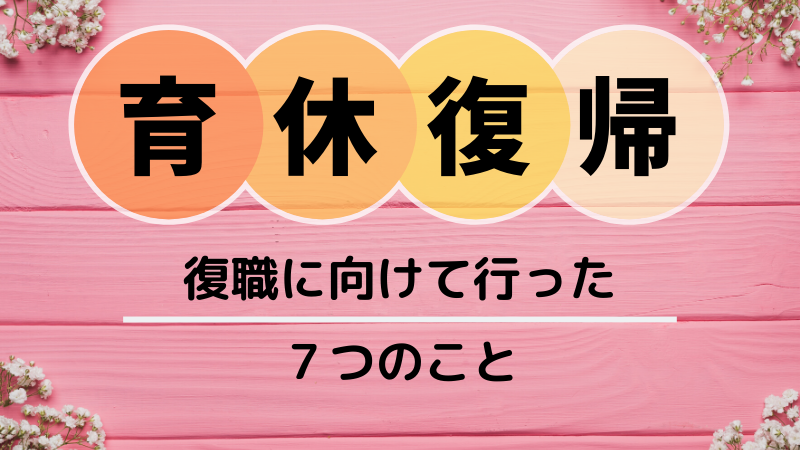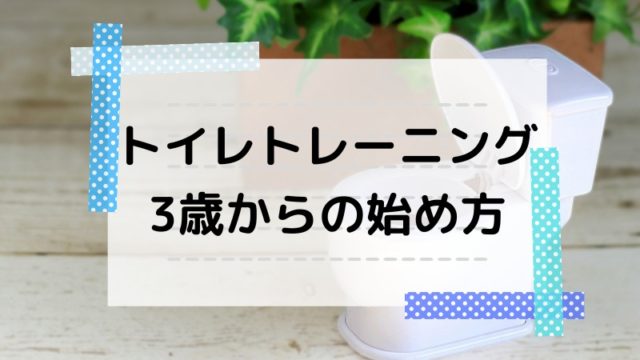この記事では、これから育休復帰をする方に向けて、育休中にやっておいた方が良い準備についてお伝えしていきます。
育休復帰が近づいてきてしんどい!不安!
と感じている方はぜひ読んでみてくださいね。
・これから育休復帰をする方
・復職に不安がある方
育休復帰がしんどい時の準備~保育園の入園準備~
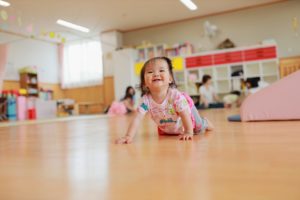
育休復帰の心配ごとの1つ。
それは、子供をちゃんと保育園に送り出せるか。
我が家も、保育園に嫌がらずに行ってくれるのか、遅刻せずに送り出せるのか、とっても不安でした^^;
保育園にはいると、それまで四六時中母親と一緒だった子どもはいきなり知らない外の世界に入ります。
最初は不安で泣いて当然ですよね。
我が子も最初は泣いてばかりでした。
そのたびに心を痛めていましたが、泣いていたのは最初だけ!
案外すぐに慣れて楽しんで保育園に行くようになりました。
スムーズに保育園に送り出せるように準備しておくと良いことをお伝えします。
①慣らし保育を利用する
2週間~1か月程度、保育園の生活に徐々に慣れていくための慣らし保育の期間を設定できます。
慣らし保育では、最初は午前中の数時間、慣れてきたら半日、それから1日、と少しづつ時間を延ばしていきます。
私の場合は4月1日を育休復帰日としていたため、3月からの慣らし保育は受け付けてもらえませんでした。
そのため、育休復帰日をずらすわけにもいかず、仕事も休めないので、慣らし保育はせず、ぶっつけ本番になってしまいました。
慣らし保育の期間を設けたい場合は、育休復帰のタイミングを4月半ばか5月くらいからにしておく方が良さそうですね。
慣らし保育ができない代わりに、一時預かりのできる保育園に何度か預かってもらい、同年代の子たちとの共同生活に慣れておくようにしました。
②入園グッズの準備
保育園によって用意するものが指定してあります。
入園説明会で、分からないことなどは事前に確認しておきましょう。
ちなみに私が準備したものは以下です
1歳児クラスの準備物(例)
- 保育園バッグ
- 絵本バッグ
- お食事エプロン10枚
- お手拭き10枚
- ビニール袋
- お名前スタンプ
- お名前タグ
- 多めの着替え
私の保育園では3月末に入園説明会があったため、説明会を聞いてから準備しようと思うと4月1日まで時間がありませんでした。
そのため、事前に園に連絡をし、大まかな準備物は直接電話にて教えてもらいました。
園によっては、手作りのエプロンやカバンなどを指定されることもあるので、準備に時間がかかりそうなら早めに問い合わせてみることをお勧めします。
③子どもが病気をしたときの対応をチェック

保育園に通いだすと、子どもは必ず体調を崩します。
感染症にかかると、2~3日は保育園を休まないといけなくなり、仕事にも支障をきたします。
いざというときに慌てないように以下の準備をしていました。
- 病児保育の登録
- ファミリーサポートの登録
- 小児科をチェック
病児保育の登録
病児保育をやっている場所を調べて、事前登録をしておきましょう。
病児保育は定員制で数に限りがあるので、利用したいときにいっぱいで預けられなかった!ということもあります。2、3か所は登録しておきたいですね。
また、利用の際に医師の診断書がいる場合もあります。
かかりつけの病院に書いてもらう用紙は事前にコピーし、すぐに使えるように自宅に保管しておきます。
夫と共有しておくことも大切です!
ファミリーサポートの登録
ファミリーサポートは、地域で子育ての支援をするために、育児の援助を受けたい方(依頼会員)と育児の援助を行いたい方(提供会員)が会員登録をし、提供会員が依頼会員に対してさまざまな育児の手助けを有償で行う会員組織です。
例えば、このようなサポートが受けられます。
- 保育施設等までの送迎を行う。
- 保育施設の開始前や終了後又は学校の放課後、子どもを預かる。
- 保護者の病気や急用等の場合に子どもを預かる。
- 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際、子どもを預かる。
- 買い物等外出の際、子どもを預かる。
- 病児・病後児の預かり、早朝・夜間等の緊急預かり対応
こちらも、事前登録が必要になりますので、忘れずにしておきましょう。
両親が遠方で頼る人がいない、というときに頼れる存在になってくれるはずです。
いざというときに駆け込める小児科をチェック
ちょっと調子が悪いな、と感じたときに保育園帰りにすぐに行ける小児科を探しておきましょう。
行きたいときにかかりつけの病院が休みだったりすることもあるので、近所で行きやすいところを何個か探しておくと良いですね。
また、夜間や休日もみてくれる病院もチェックしておきましょう。
育休復帰がしんどい時の準備~復職に向けての準備~
育休復帰で仕事を再開するにあたって、いくつか準備しておきましょう。

①仕事内容のおさらい
私は産休に入る前とは全く違う役割になったため、事前に勉強できるところは勉強しました。
また、以前その役割をしていた人に連絡をとり、仕事のおおまかな内容や勉強しておいた方が良いことなどを教えてもらいました。
そうすることで、多少のイメージはつき、事前の心構えもできました。
産休・育休の間に業務内容も変わっている場合がありますので、事前に確認できるところはしておきたいですね。
②1日のシミュレーションをする
朝起きてから会社に行くまでをシミュレーションしました。
子どもがなかなか起きてくれなかったり、朝ごはんを食べなかったり、準備が進まなかったり、予想外のことが起きるので、かなり余裕をみておいた方が良いということが分かりました。
保育園の送り迎えのルートも事前に確認しておくといいですね。
我が家は自転車にしたので実際に子供を乗せて試乗もしました。

③仕事で使う準備物の整理
会社で使う道具や制服などはあらかじめ持って行き、ロッカーに入れてスタンバイ。
いつでも仕事がスタートできる状態にしておきました。
仕事復帰初日はただでさえ緊張でいっぱいいっぱいなので、準備しておいたおかげで忘れ物もなくスムーズに仕事が始められました。
初日は挨拶用の菓子折りを持って行くぐらいで済みましたよ。
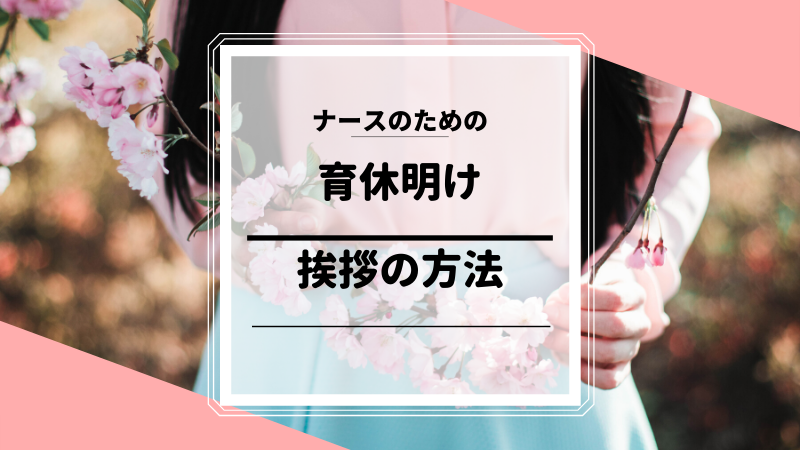
育休復帰がしんどい時の準備~夫婦で役割を共有する~
子どもの送り迎えの役割分担、家事分担などはよく話し合って決めておくことが大切です。
夫は忙しい日々を乗り越えるための心強いパートナー。
お互いに協力していきたいですね。
また、保育園グッズの定位置を決め、共有しておくことで探し物の時間が減ります。
よく使うもの(文房具やオムツ、連絡帳など)やいざというときに使うもの(母子手帳、健康保険証、病気をしたときに書いてもらう医師の診断書など)は特に定位置を決め、場所を共有しておきましょう。
また、復職してから、フルタイムで働くのか、時短勤務で働くのかについても事前にパートナーと相談しておきましょう。

育休復帰がしんどい時にする準備 まとめ

以上が私が復職に向けて実際に行った準備になります。
保育園に通いだすと、子どもは想像以上に病気をします。
仕事も休みがちになるのは仕方のないことです。
子どもも新しい生活に慣れるために頑張っています。
仕事を休んで迷惑をかけるのは当たり前と思って、周りのスタッフに協力してもらえるような関係づくりをちょっとづつでもしていけたら良いですね。
また、復職してしばらくは慣れない生活にストレスもたまりやすい時期です。
自分ひとりで背負い込もうとせず、夫にも最大限頼りながら乗り越えていきたいですね。
仕事にも慣れてきて、自分のペースをつかめるようになったら大分楽になると思いますので、それまで頑張りましょうね^^